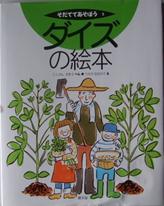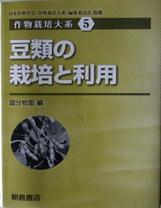○ 研究紹介
1.CO2濃度・気温に対するダイズの反応
大気CO2濃度と気温は上昇を続けており,将来の作物生産は高CO2濃度・高気温条件下で行わなければなりません.高CO2・高温条件で能力を発揮できるダイズ品種・栽培法の開発が必要です.東北農業研究センター(盛岡)に設置されているCO2濃度と気温の制御が可能な施設(グラディオトロン)を活用し,下記の課題に取り組んでいます.
① 窒素固定能の異なる品種・系統の高CO2・高温条件への適応性:
イネ科作物においては,高CO2・高温による生育促進には窒素の供給能が影響することが知られていますが,マメ科作物の窒素固定能の影響については不明です.高CO2・高温下では,光合成や物質生産能が生育前期では促進されましたが,生育後半では物質生産能が低下する,いわゆる“ダウンレギュレイション”が窒素固定能の高いスーパーノジュレイション系統においても認められました(Matsunami et al. 2009, Otera et al. 2011).
②伸育型が異なる品種・系統の高CO2・高温条件への適応性:
伸育型(有限型/無限型)は生育中期以降の物質生産量(シンク受容能)に大きな差があることから,両型間では上記のダウンレギュレイションの発現が異なることが想定されます.そこで,伸育型の異なるアイソラインを用いて高CO2・高温条件における反応を解析しています.
(今後の課題)
・ 高CO2・高温条件における窒素栄養(固定能,施肥窒素と窒素の利用効率)の最適化
・ ダウンレギュレイションの発生機構の解明
詳細は下記の文献をお読みください.
・Matsunami T et al. 2009. Effect of CO2 concentration, temperature and N fertilization on
biomass production of soybean genotypes differing in N fixation capacity. Plant Production
Science 12: 156-167.
・Otera M et al. 2011. Is yield enhancement by CO2 enrichment greater in genotypes with a
higher capacity for nitrogen fixation? Agricultural and Forest Meteorology 151:1385-1393.
← グラディオトロン内部で生育中のダイズ.奥が高温区,手前が低温区. ○この研究には,松波寿典さん,大寺真史さん,田部井浩子さん,海燕さん,Mochamad Arief Solehさん,今野智寛さんらが参画.

2.ダイズのシンク形成機構の解明
ダイズは開花数は多いのですが,落花・落莢が多いため結莢率が低いことが知られています.ダイズ花房内の結莢率変動は内生サイトカイニン(CK)含有率と相関があり,花房へのCK施与は結莢率を高めること(Nonokawa et al. 2007)が知られています.根で合成されたCKが花房に輸送され,結莢促進に寄与すると想定されることから,土壌の理化学性が根系のCK合成に影響し,地上部へのCKの供給を通じてダイズの結莢に大きく影響していると推測されます(Kokubun 2011).そこで,
「土壌の理化学性の改良」→「根のCK合成を活性化」→結莢率増加
の仮説を検証しています.この研究が進展すれば,ダイズの結莢率を飛躍的に増加させることが可能になるかもしれません.
詳細は下記の文献をお読みください.
・Nonokawa K et al. 2007. Roles of auxin and cytokinin in soybean pod setting. Plant Production Science 10: 199-206.
・Kokubun M 2011. Physiological mechanisms regulating flower abortion in soybean. In Tzi Bun Ng ed., Soybean Biochemistry, Chemistry and Physiology. INTECH. 541-554 (Open access book).
← ダイズの花房の開花後の発達過程(写真:野々川香織). DAA: 開花後日数 ○このテーマには,八島由美さん,野々川香織さん,笠原僚さんらが参画.

3.ダイズの冠水耐性機構
ダイズの湿害の一つとして播種後の冠水による発芽率の低下があげられます.この発芽率の低下には,急激な吸水による種子の物理的な破壊のほかに,冠水にともなう土壌中の酸素量の減少が影響している可能性があります.冠水に強い品種は種皮および糊粉層における水の侵入抵抗が大きく,それには種子の内部構造が関係していることがわかりました(Muramatsu et al. 2008).遺伝的/栽培手段により冠水耐性を強化する方策を検討しています.
←ダイズ種子の断面写真(写真:田小海). ○このテーマには,田小海さん,村松直さんらが参画.現在,中嶋孝幸さんを中心に実施中です.

詳細は下記の文献をお読みください.
・Muramatsu N et al. 2008. Relation of seed structures to soybean cultivar difference
in pre-germination flooding tolerance. Plant Production Science 11: 434-439.
・国分牧衛・島村聡. 2010. 作物の冠水害・湿害, ダイズ. 坂上潤一他共編, 湿地環境と作物.
養賢堂. 156-162.
4.イネの水分吸収・利用効率の遺伝的変異
イネの生産性維持・向上には充分な水と窒素肥料の供給が不可欠です.近年,気候変動などにより世界の主要な稲作地帯では水不足が懸念されており,水・肥料を節減した条件下で生産性の高いイネの遺伝的改良と栽培法開発が重要です.これまで,アジア・アフリカ稲の種間交雑であるネリカ品種群の特性を解析し,土壌水分と窒素肥料の少ない条件で多収性を発揮する系統があること,それには水と窒素の吸収能力が寄与していることを見いだしました.また,世界のイネ品種の遺伝的変異を網羅するイネコアコレクションを材料に,水の吸収・利用効率の高い品種の抽出とその生理学的基礎について研究しています.この研究は,松波麻耶さんらが中心となり実施しています.
詳細は下記の文献をお読みください.
・Matsunami M and Kokubun M 2011. Yield response of upland NERICAs under rain-fed upland conditions with different levels of nitrogen application. JARQ 45: 243-249.
・Matsunami M et al. 2012. Genotypic variation in biomass production at the early vegetative stage among rice cultivars subjected to deficient soil moisture regimes and its association with water uptake capacity. Plant Production Science 15 (in press).
5.ダイズの耐塩性の機構解明(2011年開始)
2011.3.11の津波により,多くの農地が塩害を受けました.また,世界には多くの塩類集積土壌が分布しており,作物の生育を阻害しています.塩害によるダイズの生育阻害の機構と耐塩性品種の特性を解析しています.
○ 教育活動
1.主な授業科目
・学部:食用作物学,資源作物学など
・大学院:作物生産学特論,生物機能科学など
2.教科書・参考書など
1) 幼児/小学生対象
・こくぶんまきえ へん.1998. そだててあそぼう「ダイズの絵本」.農文協.
・国分牧衛. 2005. すがたをかえる大豆. 小学校教科書 国語三下. 光村図書,22-25.
2) 学生/研究者/技術者対象
・国分牧衛. 2010. 新訂食用作物. 養賢堂
・喜多村啓介,国分牧衛他編. 2010. 大豆のすべて. サイエンスフォーラム.
・国分牧衛編. 2011. 作物栽培大系5 豆類の栽培と利用. 朝倉書店.
3) 一般読者対象
「歴史を動かした作物の群像」(仮題):準備中.