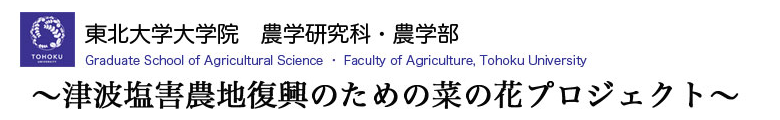よくある質問
東北大学菜の花プロジェクトにいただく質問をまとめました。お問い合わせの際に、ご一読ください。
東北大学の耐塩性菜の花の分与は可能ですか?
東北大学菜の花プロジェクトで栽培した‘キザキノナタネ’の分与を希望される方は、こちらまでお問合わせください。数量には限りがありますので、ご希望に添えない場合もございます。予めご了承ください。
お問い合わせ先⇒ info※nanohana-tohoku.com (※を@に変更してください)
‘キザキノナタネ’とは何ですか?
独立行政法人農研機構東北農業研究センター(岩手県盛岡市)が育種した品種で、多収性で、耐寒性にすぐれた油糧用の品種です。
景観形成向け・花卉向け等の品種の一部には、動物が摂取すると有害なエルシン酸(エルカ酸とも呼びます)という成分が含まれるものがありますが、‘キザキノナタネ’はエルシン酸を含みません。
菜の花は基本的にどのように栽培しますか?
‘キザキノナタネ’は秋に蒔きます(下記も参照のこと)。仙台では4月下旬~5月上旬に花が咲き、種(タネ)が熟して収穫できるようになるのは7月頃です。薹(とう)のたった茎・花蕾も食べることが出来ますが、その場合、開花前、つぼみが膨らむ前が適しています。あくまで目安ですので、品種や気候により変わります。
‘キザキノナタネ’の種まきの時期はいつ頃ですか?
東北地方では秋に蒔きます。具体的に仙台では9月下旬から10月上旬です。
キザキノナタネは播種後秋~初冬にかけ、盛んに葉を繁らせます。冬期は成長が止まり、初春に成長を再開させます。新葉の成長が見られるとともに、基部には花芽が出来、やがて花茎が伸びてきます(抽苔(ちゅうだい)といいます)。播種後寒くなると、充分に成長ができないため、結果的に翌年の種(タネ)の収量が落ちる原因になります。
種まきはどのような方法で行いますか?
簡便な方法としては「ばら播き」があります。「ばら播き」での播き方は文字通りですが、種(タネ)の大きさも微小なため、均一に播種するのは難しいです。ペットボトルに石灰(どこまで蒔いたか分かるように色づけのため)と種(タネ)を一緒に入れ、一定面積に定量で播き終わるように調節しながら播く、などの方法があるようです。
また畝をたてて播く場合、「条(すじ)播き」や「点播き」の方法があります。「条播き」は畝の上に細い帯状に種を播いていきます。種(タネ)を播いた上から土を軽くかぶせていき(覆土)、その土を軽く手で押します(鎮圧)。「点播き」の場合は点と点の間(株間)を25〜30cm程度とし数粒ずつ播き、その上から軽く土をかぶせ、覆土・鎮圧します。播種した種(タネ)が多かった時には、1点あたり2株程度になるように発芽後に間引きをするとよいでしょう。 東北大学菜の花プロジェクトでは、50cm幅の畝をたてて、播種機「たねまきごんべえ」を使って、ナタネ専用のベルトを着けて「点播き」播種をしました。この場合、10aあたり500gの種(タネ)を使用しました。人力で播種した際には、株間25cm間隔で点播きをしました。
肥料はどのようなものを使われていますか?
普通に購入できる化成肥料、有機肥料(堆肥)などです。肥料の3要素は窒素(N)、リン酸(P)、カリウム(K)です。いろんな比率で配合された肥料がありますのでどれでもよいのですが、目安として10aあたり窒素量で4〜8kgとなるよう施肥するのが一般的です。また、初春に抽苔が始まる前に追肥をしてください。10aあたり窒素量で4kg程度でよいでしょう。
一昨年(2011年〜2012年シーズン)東北大学菜の花プロジェクトで使用した農地は、もともと水田や畑として利用されていて、土づくりが十分できていた農地でしたので、肥料切れはほぼありませんでした。しかし、今年(2012年〜2013年シーズン)栽培している農地は、耕作放棄地だったり砂壌土で肥料が切れやすかったりする土地ですので、施肥は多めにする必要がありました。
育て方のコツなどがあれば教えて下さい。
セイヨウナタネは、湿害には強くありません。水はけの悪い土壌で栽培する場合には畝を高めにするなどの措置が必要です。
また、抽苔前に追肥することをお勧めします。
近年エルシン酸を含まない品種が多く開発されています。栽培中にこれらの品種がエルシン酸を含む品種・系統と交雑すると、エルシン酸を含む種が混ざってしまいますので、エルシン酸を含む品種・系統と離して栽培するよう注意が必要です。
セイヨウナタネとカブは交雑しますか?
一般に、種が違うとその間では雑種は出来ません。しかし、セイヨウナタネ(学名はBrassica napus)は、カブやハクサイ、コマツナなどを含む種(学名はBrassica rapa)が持つ染色体と、キャベツやブロッコリー、カリフラワーなどを含む種(学名はBrassica oleracea)が持つ染色体をあわせ持った種であり、Brassica napusとBrassica rapaとの交雑では、種内の交雑ほどではありませんが、比較的よく種子が出来ます。雑種が出来る程度には、いくつか報告がありますが、研究報告によって結果が異なります。Brassica rapaとBrassica napusの混植試験で、Brassica rapaの母から得られた種子の0.7%が雑種で、Brassica napusの母から得られた種子の4.8%が雑種であったと報告されています(Bingら1996)。用いられたBrassica rapaはEchoという品種です。一方、同じくカナダで行われた混植試験で、Brassica rapaの母から得られた種子の14%がこれらの種間の雑種であったという報告もあります(Warwickら2003)。用いられたBrassica rapaはカナダで自生しているものです。交雑率が大きく異なる原因が、材料とした植物の遺伝的な特性の差なのか、調査した方法の差なのか、温度などの環境要因なのか、誤差が大きいからなのかは分かりません。
一方、Brassica napusとBrassica oleraceaとの間では、ほとんど雑種種子が得られません。Brassica napusの種が成立する原因となったBrassica rapaとBrassica oleraceaの間の交雑では、更に雑種種子が得られる可能性が低いです。
下記の表もご参照ください。
もしもカブが交雑した場合、カブの形に影響はでますか?
セイヨウナタネとカブが交雑した場合、雑種の根の肥大は不良となります。一般に、種内での交雑においては、根が太るものと太らないものの間の雑種は、根が太ります。しかし、セイヨウナタネとカブの雑種は、なぜか根があまり太りません。カブの他品種との交雑が起こった場合と同様に、雑種は形態が異なるため、もとのカブとの区別がつきます。
その子孫が広がる可能性はありますか?
セイヨウナタネとカブの雑種は、三倍体であり、種子は少し(セイヨウナタネの1/10程度)しか取れません。そのため、雑種がそのまま広がることはありません。雑種では、カブの花粉と同じ染色体数を持つ花粉がごくわずかに生じ、その雑種の花粉がカブの雌しべに受粉された場合、種子が出来、カブと同じ染色体数の植物が生じます。セイヨウナタネ由来の染色体を持つカブが出来るので、セイヨウナタネの染色体に競合上有利な遺伝子があれば、その遺伝子が広がります。しかし、一般のセイヨウナタネ品種では、カブの遺伝子よりも特に競合上有利な遺伝子を持っている可能性は低いので、セイヨウナタネとカブの雑種の子孫が広がる可能性は極めて低いと考えられます。品種の場合は、その子孫は、もとの品種と特性が異なるので、注意しておれば混ざることはありません。
セイヨウナタネと交雑しやすい種類は何ですか?
前述のように、カブやハクサイ、コマツナなどを含むBrassica rapaです。カラシナ(種名はBrassica juncea)も比較的交雑しやすい種で、セイヨウナタネと混植した場合、カラシナ植物体から得られた種子中の1.6%が雑種であったと報告されています
(Tsuda et al. 2012)。 3〜4.7%という報告もあります。Brassica oleraceaとの間では、手で交配しても雑種種子がほとんど得られません。ダイコンの野生植物であるセイヨウノダイコン(種名はRaphanus raphanistrum)との組合せでは、得られた32,821粒の種子の内1つが雑種であったと報告されています(Warwick et al. 2003)。
セイヨウナタネをそばに播いてはいけない作物はなんですか?
特にセイヨウナタネが他の作物の生育に悪影響を及ぼすようなことはないので、セイヨウナタネをそばに播いてはいけない作物はありません。しかし、カブやハクサイ、ツケナなどのBrassica rapaの品種の採種を行う場合は、セイヨウナタネを栽培している畑から少なくとも500メートルは離して行った方が良いでしょう。カブやセイヨウナタネなどアブラナ類の品種の採種は、一般に、同種の異なる品種からは500〜1,000 m以上隔離して行います。Brassica rapaとセイヨウナタネでは、雑種形成率は低く、雑種の種子稔性も低いので、カブなどの在来品種にセイヨウナタネの遺伝子が入ってくる可能性は低いですが、注意は必要です。
交雑しやすいアブラナ科の作物はどのような組み合わせですか?
ハクサイやカブの仲間とダイコンとの交雑では、よく交雑する品種としない品種があります。聖護院カブはダイコンの花粉で種子を付けやすく、チーフハクサイはダイコンの花粉ではほとんど種子を付けません。その特性の違いの原因となる遺伝子がある染色体の領域を明らかにしていて、その候補遺伝子を見出しています。この遺伝子が、セイヨウナタネとの交雑でも雑種種子の得やすさに影響するかどうか興味深いところです。
被災地沿岸で野生のアブラナを見ますが、これは何でしょうか?
カラシナだと思いますが、その写真があれば分かるかも知れません。葉や種子などのサンプルがあれば、確実に分かります。アブラナ類は、聖護院カブと聖護院ダイコンの区別がつきにくいように、形態だけでは種の同定が難しいことが多いので、種の簡易同定法を開発しました。新鮮な葉のサンプルをお送りください。出来れば後で、種子もお送りいただければ、塩害に強いセイヨウナタネ品種を作る上で役立つ可能性があり、ありがたいです。
日本の海岸には、ハマダイコン(Raphanus sativus var. raphanistroides)がよく生えています。これは、海水が打ち寄せるところのすぐ近くに生えていて、少し内陸に入ると、他の植物との競合に負けてしまいます。塩害にはかなり強いことが予測され、実際、塩水処理試験で塩害に強いことを確認しています。一方、カラシナは、日本中の河川敷に多く生えています。セイヨウナタネやBrassica rapaの自生は稀です。遺伝子組換えナタネが、輸入された港から搾油工場に運ばれる途中で落ちこぼれて、道路沿いに生えているのが確認されていますが、これが畑や河川敷の雑草として広がってはいません。これは、セイヨウナタネが日本での自然環境で適応していく能力が、カラシナに比べて低いからであろうと考えられます。
| ● アブラナ科の植物 | |
| アブラナ属 イヌガラシ属 イヌナズナ属 エゾスズシロ属 オオアラセイトウ属 オランダガラシ属 カキネガラシ属 |
カラクサナズナ属 ダイコン属 タネツケバナ属 ナズナ属 マメグンバイナズナ属 ヤマハタザオ属 ワサビ属 |
【参考資料2】
| ● アブラナ属 Brassica の作物 | |
| B. juncea カラシナ | B. napus セイヨウアブラナ |
| カラシナ(芥子菜) var. cernua ザーサイ(搾菜) var. tumida タカナ(高菜) var. integrifolia |
|
| B. oleracea ヤセイカンラン (野生甘藍、キャベツ) | B. rapa ラパ |
| カイラン(芥藍) var. alboglabra カリフラワー var. botrytis キャベツ(甘藍) var. capitata ケール(ハゴロモカンラン) var. acephala ハボタン f. tricolor ブロッコリー var. italica メキャベツ(芽キャベツ) var. gemmifera |
アブラナ(在来種) var. nippo-oleifera カブ(東洋系蕪) var. glabra コマツナ(小松菜) var. perviridis サイシン(菜心) var. utilis チンゲンサイ(青硬菜) var. chinensis ノザワナ(野沢菜) var. hakabura ハクサイ(白菜) var. pekinensis ミズナ(水菜) var. nipposinica |
※これらのご質問にない場合は、東北大菜の花プロジェクト事務局へお問い合わせください。
お問い合わせ先⇒ info※nanohana-tohoku.com (※を@に変更してください)