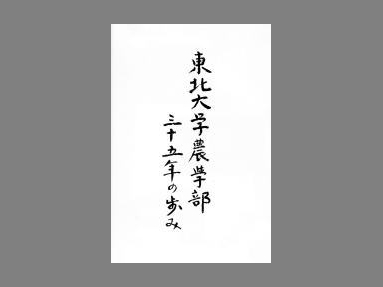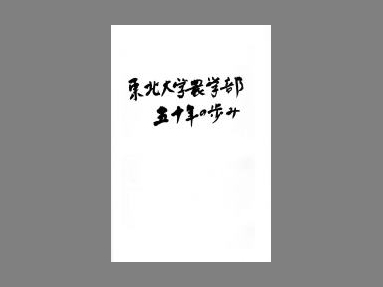研究室の沿革
草地農業研究施設(学内的俗称)(1959-1971)
草地研究施設(1971-1995)
陸圏修復生態学分野(1995-2003)
陸圏生態学分野(2003-2022)
草地-動物生産生態学分野(2022-現在) の沿革
2025.1.31更新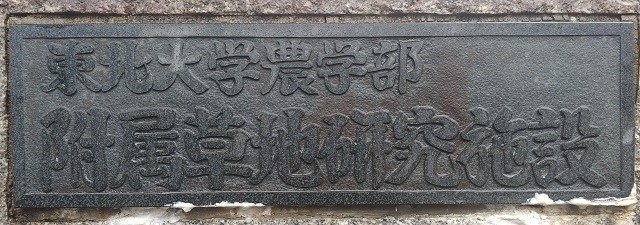
本研究室の前身である東北大学農学部附属草地研究施設は,1971年4月に設置され,24年間にわたり国立大学におけるわが国唯一の草地学専門の研究施設として研究活動を行ってきた。しかし農学部における教育研究整備の一環として,同施設は1995年3月をもって廃止され,同年4月より農学研究科に大学院独立専攻(学部を兼務としない)として新設された環境修復生物工学専攻の基幹講座(環境修復生態学講座)に陸圏修復生態学分野として転換がはかられた。研究施設の廃止・大学院独立専攻基幹講座への転換にあたりここにその沿革を記すものである。
当研究施設設置までの経緯は,東北大学農学部35周年記念誌に「草地研究施設」の記実があるので,はじめに開設までの記載部分をそのまま転記すると以下の通りである。「東北大学農学部附属草地研究施設が管制化されたのは昭和46年度であるが,その前身は,昭和34年度に草地研究のために教官定員2名(助教授,助手)が川渡農場内に認められ,「草地農業研究施設」と学内的に俗称されたものに由来する。」定員化を得た草地研究の助教授として,昭和36年11月に林兼六が,助手として昭和37年2月に小島邦彦が着任した。2人の研究活動は農学部・農学研究所・農場の共同利用となっていたブロック建ての「草地農業実験所」をベースに,実験室および試験圃場を整備することから開始された。
「草地研究室」(教官2名のほか技官3名)における研究は,林が「草類の嗜好性」,小島が「草類炭水化物の生理特性」を主テーマとし,研究室をあげての研究としては「牛の放牧による肉生産」を採りあげた。この研究には,農場教官として着任した太田実助手(現助教授)も参画し,昭和40年代末まで10年以上いろいろの形で継続された。昭和44年3月末に,小島助手が農学部土壌肥料学講座へ転出したため,同講座博士課程修了直後の菅原和夫を採用した。菅原助手の研究内容は,小島助手のそれに類似したものであったが,放牧関連の研究にも積極的に参加した。昭和46年度に,草地研究施設の草地利用部門が,農場の教官定員2名(助教授,助手)の振替えで認められ(教授,助教授,助手の教官定員3名のみ),まず林が昭和47年2月に教授として選考された後,菅原助手が昭和47年7月に農場定員から振替えられ,さらに昭和48年8月に伊藤 巌が助教授として着任した。伊藤助教授の研究は,放牧草地の生態に関するものが主であった」(故林兼六教授の記述による)・・・・
3名の教官の研究分野は,林教授は家畜生産の全般にわたるが,経営学的観点から土地利用と低コスト家畜生産について,伊藤助教授は生態学的見地から草地および家畜生産系を解析するもの,菅原助手は土壌肥料学を基礎に牧草の栄養生理と放牧地の物質動態を解明するというものであった。部門増が実現するまで草地利用一部門で草地研究全般をカバーしたいとの理由から専門の異なる教官よりなる陣容となったが,牛の放牧生態を中心とする「土-草-家畜の相互関連性の解明」という観点でそれぞれの研究が強い接点をもって進められた。
1982年11月林教授が還暦を前にして急逝した。1984年8月伊藤巌が教授に昇任,1986年1月菅原和夫の助教授昇任にともない,同年4月に大竹秀男を助手として採用した。大竹助手は本研究室出身の大学院博士過程修了者で,学生時代からの研究テーマであった「放牧家畜地の外部寄生虫であるダニの生態と放牧地環境」に関する研究を継続して行った。
1990年3月,大竹助手が宮城県農業短期大学に講師として転出するにあたり,博士過程修了後本研究室の大学院研究生であった西脇亜也を同年4月より助手に採用した。西脇助手は植物生態が専門で,特に植物の繁殖戦略に関する研究に主体がおかれていたが,野草地の放牧利用や放牧牛群の構造解析など本研究室の放牧に関する研究の推進も担った。
1992年3月伊藤教授が退官し,翌1993年2月菅原が教授として昇任した。1994年4月,本研究室の博士課程修了者であり家畜行動・家畜福祉を専門とする佐藤衆介を宮崎大学助教授から本研究施設助教授としてむかえた。1995年3月31日付で草地研究施設が廃止され,同年4月1日より農学研究科に新設の環境修復生物工学専攻・環境修復生態学講座・陸圏修復生態学分野に転換されることとなり,菅原・佐藤・西脇は陸圏修復生態学分野に配置換えとなった。
草地研究施設は大学におけるわが国唯一の草地研究機関というユニークな存在であり,しかも近年環境調和型農業が志向されるにあたり,その研究の発展が益々重要性を増しているところから,施設を廃止することが妥当か否かについて長期にわたり議論がかわされた。また当事者として研究施設の名を消すことは忍びがたいものがあった。しかし全学部的将来計画のなかで,農学に対する社会的要請に答えるには,研究教育対象を草地からより広く陸圏に拡大する発展的転換が望ましいとの結論に達し,当施設の廃止転換がはかられる事となった。
1999年2月,西脇助手が宮崎大学農学部地域農業システム学科地域農林システム学講座農林生産学研究室助教授として転出した。さらに2002年3月,佐藤助教授が独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構(農研機構)畜産草地研究所に放牧管理部長として転出した。それにともない,2003年4月に本研究室の博士課程修了者であり放牧反芻家畜の養分摂取-草類の消化-養分利用を専門とする小倉振一郎を宮崎大学助手から本研究室助教授として迎えた。また2003年4月1日より,大学院改組にともない,本研究室は農学研究科応用生命科学専攻・環境生命科学講座・陸圏生態学分野に転換された。
2005年3月菅原教授が退職し,同年4月農研機構畜産草地研究所より佐藤衆介が教授として着任した。佐藤は研究室のキーワードを「21世紀型放牧技術の構築-持続・環境・動物福祉」とし,動物行動学および福祉学を主テーマとして,家畜の放牧による福祉性向上に関する研究を通じて動物行動学を草地学分野の中で発展させた。2008年10月佐藤教授は株式会社イシイの寄附を受け,わが国初となる家畜福祉学寄附講座(イシイ)を設立し,教授として兼務した(准教授として二宮 茂,助手として小原 愛を採用)。2011年4月からは株式会社イシイに加え,日本ケンタッキーフライドチキン株式会社、有限会社北海道種鶏農場、プライフーズ株式会社等の寄附により継続され,2015年3月まで家畜福祉学の発展に貢献した(助教として親川千紗子を採用)。
またこの間,助教(任期付)の採用が認められ,東京大学大学院農生命科学研究科で博士課程後期を修了した吉原 佑を2009年4月に採用した。吉原は,モンゴル草原を中心に生物多様性の生態系機能の解明に関する研究を展開し,2016年3月三重大学生物資源学部准教授に転出した。なお,2007年4月に教員制度が改正され,「助教授」が「准教授」へと名称変更され,さらにそれまでの助手が「助教」(博士の学位を有し,授業を担当したり独立して研究を行ったりする者)と「助手」(教育研究の補助に当たる者)に分けられた。
2011年3月に発生した東日本大震災および原発事故を受け,佐藤は避難区域に取り残された家畜の保護を強く訴え,被災状況の調査を行った。同時に,小倉は川渡フィールドセンターの山地放牧地における土壌および植物の放射性セシウム汚染の実態と除染の効果を調査した。
2015年3月佐藤教授が退職し,2016年4月小倉准教授が教授に昇任した。佐藤教授が掲げた「21世紀型放牧技術の構築-持続・環境・動物福祉」を受け継ぎ,多様な植生下における放牧家畜の摂食行動,養分摂取と利用性に関する研究,ルーメン微生物相の多様性と消化機能およびその安定性との関係解明,ススキ草地における長期に亘る生態調査,反芻動物におけるルーメン環境と福祉性との関係解明,乳牛の福祉性に関する研究,等を行っている。
2017年4月,本研究室の卒業生であり家畜行動・家畜福祉を専門とする深澤 充を農研機構東北農業研究センターから准教授として迎えた。深澤は,ヒト-家畜(ウシ)間の良好な関係を構築するための飼育技術の開発,および休息行動および姿勢によるウシ飼育環境のアニマルウェルフェア評価,等の研究を行っている。また2018年4月には,九州大学農学研究院資源生物科学専攻家畜生産生態学分野(久住高原牧場)で博士課程後期を修了し,鹿児島大学農学部でプロジェクト研究員として勤務する柿原秀俊を助教(任期付)として採用した。柿原は,放牧家畜と生態と管理に関する研究を行っていたが,当研究室に着任後は,土壌-植物間相互作用に関して,主に強酸性火山灰土壌におけるイネ科牧草の永続性に関わる要因の解明に関する研究を行った。2022年3月,柿原助教は農研機構西日本農業研究センター大田拠点に転出した。
2022年4月より,大学院改組にともない,本研究室は農学研究科生物生産科学専攻・動物生命科学講座・草地-動物生産生態学分野となった。この改組を機に,当研究室が設置されてから1995年3月まで研究室名に掲げていた「草地」の名称が再び研究室名に掲げられた。草地生態系における生物間相互作用を解明し,持続的な草地生産と家畜生産システムの構築を目指すという意味が込められている。
柿原助教の転出に伴い,助教(任期付)の採用が認められ,反芻動物における摂取飼料-ルーメン発酵-行動反応性の関係解明を行い博士課程を修了した乾日格(テンルコ)を2024年4月に助教として採用した。
<現旧教員の主な受賞実績>
1976年度 日本草地学会研究奨励賞 菅原和夫「草類の可溶性炭水化物の生理化学的研究」
1990年度 日本草地学会賞(斎藤賞) 伊藤 巌「永年放牧地における牧草生産と家畜生産に関する生態学的研究」
2003年度 東北畜産学会学術賞 大竹秀男「土-草-家畜系におけるダニ類の生態に関する研究」
2005年度 日本草地学会研究奨励賞 小倉振一郎「生態学的・ルミノロジー的手法による植物-反芻家畜間相互作用の解析:放牧家畜の草選択,摂取および養分利用性の解明」
2005年度 日本農学進歩賞 小倉振一郎「放牧反芻家畜における餌選択-摂取-利用過程の実態解明」
2012年度 日本草地学会賞 西脇亜也「野草と野草地に関する生態学的研究」
2014年度 日本草地学会賞(斎藤賞) 佐藤衆介「家畜行動学ならびに家畜福祉学の草地学における展開」
2017年 日本生態学会宮地賞 吉原 佑「草原における生態系機能,生物多様性,空間的異質性,撹乱の関係を俯瞰する」
2018年 日本畜産学会功労賞(西川賞) 佐藤衆介「家畜生産におけるアニマルウェルフェア研究の推進と後進の育成」
2023年度 日本草地学会研究奨励賞 柿原秀俊「草地・放牧管理の高度化のための環境要因の解明」