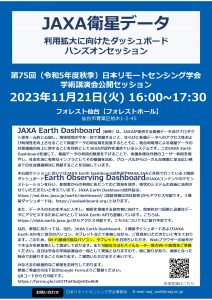次世代食産業創造センター
活動_復興農学部門
2024年7月4日(木)ミラクルフルーツを使用した食育の出前授業を行いました(福島県葛尾村小中学校)
7月4日、葛尾村小中学校にて高学年の小学生4名、中学生4名に出前授業を行いました。子供たちのほか先生方13名や給食センター、福島イノベーションコースト構想推進機構からも数名の参加があり、関心の高さが伺えました。
葛尾村での東北大の活動、特産品創出のためのすずこまトマトやマンゴー栽培の紹介の後、本題に入りました。遺伝子組み換えについて、除草剤耐性や害虫抵抗性を持つ品種を作り出すほかに、機能性物質を作物に導入することで人間の心身の健康を保つことができる新展開の話(だいぶかみ砕いて説明がなされました)を受講し、機能性物質の一例として、東北大圃場で栽培しているミラクルフルーツを用い、ミラクリンというたんぱく質により酸味が甘味として感じられるという変化を実際に体験しました。酸味のある食材としてレモン、グレープフルーツ、ぶどう、葛尾村栽培のすずこま、ヨーグルト、梅干しなどを配布、それぞれの酸っぱさを確かめてから、ミラクルフルーツを舌に付着させ、もう一度フルーツ類を口に含んで味の感じ方の前後を比較しました。先生方も含めミラクルフルーツを食べたのは初めてだったようで、全員が驚きの反応を見せておりました。東北大の葛尾での活動も紹介しました。今回の授業が少しでも興味関心を持つきっかけになったら良いなと思います。
2024年6月16日(日)「あぜりあ市」に出展しました(福島県葛尾村)
福島県葛尾村にある復興交流館あぜりあで、開館6周年を祝して「あぜりあ市」が開催されました。今年は、村民と村と関わりのある方々が葛尾らしさを生かした形となり、コンパクトでアットホームな雰囲気なイベントとなりました。
東北大ブースでは葛尾村特産品確立を目指した取り組み、カラシナ・辛味ダイコンの栽培試験と加工品試作などの活動パネルを展示し、来場者への事業説明を行いました。あぜりあに隣接する東北大圃場の植物工場の見学も2回に分けて実施し、15名の参加者は特産品としての事業化を目指しているマンゴーの遠隔栽培や開花中の花の説明、廃菌床を使用したトマト栽培についての説明に興味深そうに耳を傾けてくださいました。
2024年5月18日(土)葛尾村産トマトすずこまの苗を配布しました
5月18日(土)に葛尾村復興交流館あぜりあにて、昨年度に引き続き、すずこま苗の無料配布を行いました。当センターでは、葛尾村の新しい特産品を創出し、
希望者へは植え付けや栽培方法をお伝えしながら配布を行いました。当日の配布を含め、今年度は前回より多く、228株の配布となりました。全25名の約半数がリピーターで、昨年の栽培の様子やどのようにして食べたかなどを伺いました。
今回は収穫の余剰分が出た方には、買取りをしてドライトマトやジェラート試作品の材料とする企画を立てています。ドライトマトは活動紹介を行うために葛尾村感謝祭などにおける配布品として、ジェラート試作品の試食会も検討しております。買取を行うことで、徐々に村内での栽培が広がり、将来的には持続的な栽培・加工・販売の流れができることが理想です。商品化は郡山女子大さんの助言も仰ぎながら、関係各所と協力して進めたいところです。
2022年度から開始したすずこま苗配布イベントは今年で3回目となりました。今年度は8月下旬に収穫祭&情報交換会(仮)を予定しており、圃場のすずこま取り放題をしたり、すずこまの調理法や栽培法の情報交換をしたりする内容を検討しております。村内だけでなく近隣市町村にも周知し、更なる栽培普及に努めて参ります。
2024年3月26日(火)フィールドスペシャリストの認定を行いました
3月26日の学位記授与式にて、農学研究科長により復興農学マイスターの上位資格となるフィールドスペシャリスト認定の授与が行われました。今年は1名の認定でした。おめでとうございました。更なるご活躍を応援しております。
2024年1月13日(土)浪江町相馬市エクステンションツアーを実施しました
1月13日(土)、浪江町、相馬市を訪問するエクステンションツアーを開催しました。次世代食産業創造センターでは、東日本大震災による被害の状況、復興活動・状況を学ぶツアーを企画・運営しています。今回のテーマは、「福島県浜通りの水産業の復興・課題を学ぶ」で、学生、社会人、教員合わせて26名が参加し、2011年の東日本大震災から13年が経とうとしている今、水産業の復興の現在地、現状の課題や新しい取り組みなどについて学ぶツアーとなりました。
最初に訪れたのが浪江町請戸地区。海から目と鼻の先にあった請戸小学校は現在震災遺構として一般公開されています。津波が襲った時間で止まったままの時計、ひしゃげた鉄筋やはがれた壁が津波の威力を物語っていました。一般社団法人まちづくりなみえのガイド・石山さんより当時の状況について詳しく説明を受けました。在校していた児童は約2キロ離れた丘に手を取り合いながら全員避難して無事だったことや、集落の人々のこと、原発事故が発生し避難命令が出たため捜索ができなかったことなど、壮絶な出来事があったことを知ることができました。
その後は再建して運用が開始されている請戸漁港、水素エネルギー研究フィールドなどがある棚塩産業団地を巡り、震災後の新しい取り組みや産業について現地を見学しました。



“請戸地区ガイドツアー”
午後は福島県水産事務所次長の渋谷様、福島県水産海洋研究センター副所長の根本様より、福島県の漁業の現状や研究の役割について講話をいただきました。漁港等施設の復興は着実に進んでいる一方で、流出した漁船の回復や担い手不足にいまだ課題があることや、高付加価値化の取り組み、資源調査によるより効果的かつ効率的な漁業やおいしさを科学的に明らかにする研究がなされていることなどをご紹介いただきました。

1130071-300x225.jpg)
“福島県水産事務所渋谷次長様、福島県水産海洋研究センター根本副所長によるご講話”
その後、相馬市の磯部地区にある磯部水産加工施設を訪問しました。施設長の太田様より、近海で獲れた水産物が販売されている併設の直売所を案内していただいた後、場所を変えて、震災時の松川浦を含めた周辺の被害の様子や変化の説明を受けました。さらに、相馬双葉漁協の現状、施設の目的や役割(品質・衛生管理、放射性物質検査)についての説明がありました。津波で変容した磯部地区の復興や漁業にかける思いなども合わせてお話いただきました。


“磯部水産加工施設への訪問”
移動中のバスの車内では、大谷教授から南相馬市や浪江町で行っているアイガモロボットを使ったイネの栽培試験について、片山教授と中野准教授からは震災後の福島沿岸の海洋の生態系の変化に加え、漁協、漁業者の復旧、復興への取組み、福島水産業再生とスマート化推進に向けた研究開発について紹介がありました。また、帰りのバス車内では一人一人感想を述べ、お互いに意見、考えを共有し合いました。
今回のツアーでは、ほんの一部ではありますが東日本大震災および福島第一原発事故により復興がもっとも遅れた産業である水産業をみてきました。漁船の流出、漁港の被害、原発事故による風評被害、担い手の減少と多くの苦難により時間はかかりましたが、東京の市場等で高い評価を受けていた福島県沖の魚(「常磐もの」と呼びます)を復活させるために多くの方々の積み重ねの一端を学び、また、新しい取り組みの数々についても知ることができました。ご協力くださいました皆様、ありがとうございました。
2023年11月25日(土)福島県葛尾村産マンゴーフェスティバルを開催しました
11月25日(土)、福島県葛尾村のせせらぎ荘にて「葛尾産マンゴーフェスティバル」を開催しました。東北大学は、福島県の企業3社と共に2018年から葛尾村に設置した植物工場でマンゴー栽培をスタートし、事業化を目指して試験栽培を続けてきました。事業化するにあたり、より付加価値を高めるため、開花を遅らせてお歳暮商戦の時期に収穫する栽培体系の確立を目指しています。去年に引き続き今年も収穫時期を遅らせることができ、この時期にフェスティバル開催が可能となりました。葛尾村民をはじめ一般の方に葛尾でとれたマンゴーを食べてもらう初めてのイベントでした。

加藤准教授よりイベントの趣旨説明を、郡山女子大の学生よりメニュー紹介を行いました
葛尾産マンゴーを使ったミニスイーツを5種類(マンゴーカッサータ、マンゴープリン、マンゴーシフォンサンド、マンゴーパウンドケーキ、マンゴーラッシー)用意し、ラッシーと好きなスイーツ2種を選んで食べられる形式としました。スイーツのレシピは郡山女子大生が考案、一品ずつ品種の違うマンゴーを使い、味や色の違いを楽しんでもらいました。当日も女子大生4名がスイーツ作りや提供に協力してくれました。「おいしいです!」「プリンが濃厚」「ラッシーがさわやかでいいね」など来場者からたくさんの笑顔とともにうれしいお声を聞くことができました。

左からマンゴ―プリン、マンゴーラッシー、カッサータ、シフォンケーキ、パウンドケーキ
また、マンゴーが当たる抽選会もおこない、アンケートに答えてくれた方にくじを引いてもらいました。3名の方にキーツ種のマンゴーが贈られました。

3名の方が当選しました
アンケートには「村の特産品にしてほしい」「この時期にマンゴーを食べられてうれしい」「葛尾でマンゴーを作っていることを初めて知りました」「販売してほしい」などの感想をいただき、約90名の方に楽しんでもらうことができました。
郡山女子大学の皆様、来場者様、葛尾村関係者の皆様、ありがとうございました。

郡山女子大の学生さんにはレシピ考案から事前準備、当日の運営まで大変お世話になりました!
2023年11月3日(祝・木)かつらお感謝祭に「かつらお復興キャンパス」として出展しました
11月3日の文化の日に福島県葛尾村みどりの里広場で開催されたかつらお感謝祭に出展しました。この感謝祭は地場産業の振興を図りつつ生き生きとした地域づくりを目的とし、多くの村民が来場する秋の風物詩となっております。各種催し物で賑わう中、東北大ブースでは教員2名、学生2名、職員1名で「すずこま」(加熱調理用トマト)を乾燥加工したドライトマト(300袋)の配布と試食や、各種チラシ配布、収穫したばかりの3品種のマンゴーの展示、スマートグラス体験、復興知事業や特産品開発、植物工場IoT、カラシナ栽培等のポスター展示を行いました。

ドライトマトの配布や展示を通して多くの方と交流しました
昨年より多く準備したドライトマトでしたが、子どもからお年寄りまで人気で祭開始から2時間半で配布終了となりました。すずこまの栽培の仕方や種の入手方法、ドライトマトの作り方などをたずねる方が多くいました。また、展示パネルについて熱心に質問をくださる方や、スマートグラスを体験して感心される方もいました。生マンゴーの展示では、葛尾でマンゴーが栽培されていることを初めて知ったという方もいました。
葛尾村民はじめ多くの方々と交流し、活動を知ってもらうことができた感謝祭でした。今後も様々な形で葛尾村での活動を継続していきます。

事業取組紹介ポスターや生マンゴー展示の様子

葛尾村マスコットキャラクター「しみちゃん」もブースに来てくれました
2023年11月25日(土)福島県葛尾村せせらぎ荘で葛尾産マンゴーフェスティバルを開催

*葛尾村植物工場Facebook ☞https://www.facebook.com/KatsuraoPF
*問い合わせ先 ☞東北大学大学院農学研究科 園芸学分野
加藤一幾:kazuhisa.kato.d8*tohoku.ac.jp *を@に変更してください。
2023年11月21日(火) JAXA衛星データ利用拡大に向けたダッシュボードハンズオンセッションについて(フォレスト仙台)
2023年11月に開催される日本リモートセンシング学会学術講演会の公開セッションとして、宇宙航空研究開発機構(JAXA)による衛星データ利用システムのハンズオン(利用体験)を実施します。人工衛星による観測では広域を一度にみることができます。土地利用型農業においては生育管理や収量予測などに、漁業においては漁場の探知や沿岸域での養殖漁業の管理に、人工衛星による観測画像の利用がおこなわれています。森林管理などの環境モニタリングにも活用されています。これまでデータの入手や取り扱いに専門的な知識がいりましたが、オープンデータ化が進み、誰でもインターネットからデータをダウンロードできるようになってきています。
本セッションは衛星データ利用者を広げていくことを目的としています。農業や漁業への利用にかぎらず様々な目的での利用者を想定しています。
参加にあたっては、Wi-Fi接続可能なパソコン、タブレットをお持ちください。ご自身で操作を体験していただきます。Webブラウザーの操作ができる方を参加者として想定しています。席に限りがあり、満席となった時点でお断りすることもあります。ご留意いただけますと幸いです。
参加登録は下記URLよりお願いいたします。
https://forms.gle/oS3TFaESaQvEEeAb8
*「まなびのめ」掲載ページ ☞https://x.gd/pZ8Ls
*問い合わせ先 ☞東北大学大学院農学研究科 農業経済学講座(地域資源計画学分野)
米澤千夏 :chinatsu@tohoku.ac.jp
2023年9月27日 南相馬市エクステンションツアーを実施しました
今回のエクステンションツアーは「高度ロボット技術が支える浜通りの復興」をテーマとして実施しました。当日はそれまでの暑さがひいて過ごしやすい気温となりましたが、あいにくの雨の中の出発でした。参加者は14名で、社会人3名、農学部・農学研究科6名のほか、他学部・学科より5名の参加がありました。以下に詳細を記載します。
【9/27(水)南相馬市エクステンションツアー行程】
| 8:30 | 青葉山キャンパス出発 |
| 10:30 | 道の駅南相馬到着 ボランティアガイドによる南馬市内ツアー(①下記参照)(南相馬市消防・防災センター→北泉海岸メモリアルパーク→ロボットテストフィールドを車窓から→道の駅南相馬) |
12:45 | ㈱菊池製作所(②下記参照)到着 昼食後、事業内容や共同研究の概要説明後、アシストスーツ装着体験とドローン製造過程の見学、工場内見学 |
| 14:55 | 農事組合法人あいアグリ太田(③下記参照)到着 奥村さんよりアイガモロボットを使用した圃場としていない圃場の生育状況の説明や生産性、問題点等田んぼを回わりながらの説明 |
| 15:55 | 終了 |
| 17:45 | 青葉山キャンパス到着・解散 |
①南馬市内ツアー
防災センターでは阿部さんより原発事故当時の様子や原子力災害が今も与えている影響、地震・津波だけではない様々な災害の可能性、東日本大震災を教訓とし防災意識を高める展示の説明などを受けました。メモリアルパークでは小雨が降る中ボランティアガイドの安部さんより、当時の地震直後に津波の様子を高台から眺めていた時の様子を語ってくれました。ロボットテストフィールド周辺では車窓からの見学でしたが、北柴先生よりロボット実証試験用の各種施設を見ながら、ロボットテストフィールド設立の目的や行われている実証試験の説明がありました。

防災センター訪問

北泉海岸メモリアルパークでの説明
②㈱菊池製作所
到着後すぐに会議室にて昼食をとらせていただき、その後一柳副社長より15分程度で会社概要や共同研究の取り組みについての講話をいただきました。人命救助用ロボットや脳磁計、環境クリーン事業など、これまで以上に共同研究を重ねて開発を続け社会実装していきたいという内容でした。また、佐久間先生よりNICHeの概要や、NICHeの南相馬拠点として菊池製作所内に置いていること等の説明がありました。続いてアシストスーツの装着体験があり、そこでは女子学生2名、男子学生1名が体験をし、重い荷物を持った時や中腰の姿勢で腰の負担が軽減されることを体感しました。ドローン開発セクションではEAMS ROBOTICSの開発担当者より開発中の10Lの薬剤を散布できる大型ドローンを見ながら話を聞きました。浜通りでは40機のドローンが現場で利用されており、ユーザーのフィードバックを得ながら改善ができるのがこの地域の利点とのことで、国が定めた1種と2種の型式のうち、1種認証を受けたものは現在日本郵政の1機のみで、2種はまだ認証を受けたものはなく、それに向けて基準をクリアするための開発を行っているとのことでした。

アシストスーツの装着体験

開発中の大型ドローンの見学
③農事組合法人あいアグリ太田
無肥料無農薬+アイガモロボ稼働有り、有機栽培+アイガモロボ稼働無し、有機栽培+アイガモロボ稼働有りの3種類の水田を訪れ、イネの生育、雑草の状態などの違いなど栽培条件を見奥村さんより説明を受けました。それぞれの条件によりはっきりと差が出て、アイガモロボの効果が大きいことが見て取れました。 アイガモロボは代かき後から稼働させ田植えのときに一旦止めて田植え後また稼働させる、水位が適正でないとアイガモロボの十分な作動ができないため水位センサーを設置し7~8㎝の状態を保つことが重要である、とのことでした。雑草を除去するというよりは水流で水を濁らせ光を届きにくくすることで抑草効果がでるとのことでした。アイガモロボットだけでは完全に除草できないので機械除草も併用しているそうです。参加者から「あったらいいなという機械は?」という質問には、機械除草を1回行うだけでもだいぶ雑草が抑えられるので、その機械の作業効率が上がるように、株間と条間をある一定の基準にそろえられるような田植え機があるといいとのお話でした。現在GPS機能のついた田植え機開発が進んでいるとのことで、再来年はハウスを25棟建設、10名雇用し、トルコギキョウなど無加温で花卉栽培をやっていく計画だそうです。少しでも雇用の機会を増やし、地域の発展につなげたいとのことでした。

雨が上がり圃場へ出ての見学

アイガモロボの説明
各訪問先において、参加者より質問が出て積極的なやりとりがありました。南相馬に来るのが初めてという人も多く、今回の訪問で福島が未だ抱える問題や復興を推し進める先端技術開発、農業の再興に向けた新しい取り組みを知ってもらうことができました。帰路の途中のバス車内では、参加者より印象に残ったことや感想などを発言してもらい、抱いた思い・考えなどをお互いに共有しあいました。
ご協力いただいた皆様、誠にありがとうございました。
2023年8月6日 復興・IT農学実習を実施しました(福島県葛尾村)
今年度も東北農業の復興と日本農業の新生を牽引できる人材の育成を目的とした復興・IT農学実習が実施されました。4月からの全9回の座学の後の最終授業となる実習は、8月5日に川渡フィールドで先端農学技術を体験し、翌日、実際に葛尾村を訪問し被災地の復興の現状と課題、地域振興の取組みにリアルに触れ多くの収穫を得て終えることができました。被災地訪問の参加者数は70名と昨年度を大きく上回る数でしたが、事前に希望をとって4班に分けての視察を行うなど運営体制を整えることによりスムーズに進めることができました。
8/6午前中は葛尾村役場で松本復興推進係長より葛尾村復興の概要をわかりやすく丁寧にご説明いただきました。質疑応答では多くの学生から挙手があり、教育や農業についての関心の高さが見られました。学生からの質問は後日とりまとめられ役場に送り返答をいただくこととなりました。

“松本復興推進係長によるご講話の様子”
昼食はむらづくり公社のご協力のもと、特産品としての確立を目指している東北大植物工場で収穫した「すずこまトマト」を用いてオリジナルスパイスカレーを準備していただき、せせらぎ荘でいただきました。植物工場管理責任者である加藤准教授にすずこまトマトのご説明をいただきながら皆で食べるカレーの評判は上々で、炎天下で行われた午後の実習にも活力を与えてくれました。

“すずこまとまとの入ったスパイスカレー”
午後は4班に分かれ、うち2班は東北大学葛尾村植物工場、かつらお胡蝶蘭合同会社へ、残る2班は東北大学葛尾村植物工場、葛尾村復興交流会館あぜりあ、株式会社HANERU葛尾へバスで訪問しました。

❝胡蝶蘭合同会社への訪問❞

❝HANERUかつらおへの訪問❞

❝葛尾村復興交流会館あぜりあへの訪問❞
ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。
<8/6(日)復興・IT農学実習行程>
| 8:00~8:15 | 総合研究棟前 | 集合、受付 |
| 8:20 | 出発 | |
| 9:40 | 常磐道南相馬SA | セデッテかしまにて休憩 |
11:00 12:20 | 村民会館 | 復興の歩み講話(松本復興推進室係長) 質疑応答 |
| 12:30 | せせらぎ荘 | 昼食 |
| 13:15 | 村内各所にて班活動 | 1班:HANERU-植物工場-あぜりあ 2班:胡蝶蘭-あぜりあ植物工場 3班;植物工場-あぜりあ-HANERU 4班:あぜりあ-植物工場-胡蝶蘭 |
| 15:00 | あぜりあ | 班活動終了、あぜりあに集合、トイレ休憩等 |
| 15:15 | 出発 | |
| 16:15 | 常磐道南相馬SA | セデッテかしまにて休憩 |
| 17:55 | 総合研究棟前 | 到着・解散 |
2023年6月10日「あぜりあ市」に出展しました(福島県葛尾村復興交流館あぜりあ)
今回のあぜりあ市は葛尾村政100周年と復興交流館あぜりあ開館5周年を記念して開催されました。過去最大の33の出展数となり、開始前から大勢の来場客が訪れました。開催当初より参加している農学研究科は、他の連携大学等と共に今年も協力団体として名を連ねました。



“農学研究科ブースでのすずこま苗配布と展示”
葛尾村の特産品のひとつとして力を入れている加熱用調理トマト「すずこま」の苗を来場者に配布いたしました。配布時には農学研究科の大学院生2名により栽培の仕方や食べ方について丁寧なアドバイスがされました。リピーターが増え人気上昇中のトマトだけあって配布開始からの1時間半で全100株を配り終えました。


“植物工場内での説明の様子”
午後は葛尾村特産品を栽培している植物工場見学を行いました。1回目は17名、2回目は18名の参加がありました。もうひとつの特産品であるマンゴーの遠隔栽培や開花中の花の説明、廃菌床を使ったトマト栽培についての説明を行いました。



“郡山女子大ブースで配布された特産品として栽培しているすずこまトマト&カラシナを使ったお茶漬けとポンデケージョ”
ブースを訪れてくれた村民の方々との交流を通じて、以前より東北大の葛尾村での活動について聞いたことがあるという一般の人が増えている印象で、マンゴーを活用した村のPRや、昨年から行っているすずこま苗配布の活動によって少しずつではあるが認知度が定着しているのではないかという印象がありました。
加藤一幾(園芸学分野 准教授) kazuhisa.kato.d8*tohoku.ac.jp
北柴大泰(植物遺伝育種学分野 教授) hiroyasu.kitashiba.c7*tohoku.ac.jp
*を@に変更してください。
福島県葛尾村復興交流館あぜりあで行われた「あぜりあ市」に出展しました
2022年6月5日に福島県葛尾村復興交流館「あぜりあ」で村民との交流イベントが開催されました。 農学研究科は2016年に葛尾村と連携協定を結び、実用開発事業や福島ノベーションコースト構想の復興知事業などを通じて復興活動をしています。
「岸田総理に説明をする小倉教授と加藤准教授」
今回は、主に次世代食産業創造センターが取り組んでいる復興知の活動について紹介しました。
小倉教授、北柴教授、加藤准教授、坪井研究員が参加し、特産品開発のためのマンゴー、トマト(品種‘すずこま’)、カラシナなどの栽培・加工の実証試験の成果や、栽培管理におけるスマート技術の導入の様子など、植物工場と圃場の見学も取り入れて説明をしました。
「植物工場前での説明(北柴教授)」
また、葛尾村の一部は東京電力福島第1原発事故の影響により帰還困難区域が続いていましたが、2022年6月12日に避難指示が解除されることに伴い、その報告を直接住民に説明するために岸田総理大臣がお越しになりました。東北大学のブースにも立ち寄られ、直接活動の内容を説明しました。 当日は葛尾村や近隣市町村から総勢1000名近い来訪者があり、多くの方々が東北大学のブースを訪ね、東北大学農学研究科(次世代食産業創造センター)の取組みを知っていただき、また対面での会話を通して良い交流の場となりました。
「農学研究科のブースでの来場者への説明」
【参考リンク】
次世代食産業創造センターのFacebook
植物工場におけるマンゴー栽培の動画
【問い合わせ先】
加藤一幾(園芸学分野 准教授) kazuhisa.kato.d8*tohoku.ac.jp
北柴大泰(植物遺伝育種学分野 教授) hiroyasu.kitashiba.c7*tohoku.ac.jp
小倉振一郎(草地-動物生産生態学 教授)shin-ichiro.ogura.e1*tohoku.ac.jp
*を@に変更してください。
イノベーション体感デー2021に出展しました
あぜりあ市に出展しました
 11/1(月)にあぜりあ市に出展し、試食提供と植物工場見学、スマートグラスの体験を行いました。 試食は80-100食くらいが10時から開始し、12時には売れ切れてしまいました。 加熱調理用トマト、ミニミニカリフラワー、粒マスタード、 全て好評でした。植物工場見学ツアーも2回行い、全部で18名の参加でした。地元の親子も参加してくれました。
11/1(月)にあぜりあ市に出展し、試食提供と植物工場見学、スマートグラスの体験を行いました。 試食は80-100食くらいが10時から開始し、12時には売れ切れてしまいました。 加熱調理用トマト、ミニミニカリフラワー、粒マスタード、 全て好評でした。植物工場見学ツアーも2回行い、全部で18名の参加でした。地元の親子も参加してくれました。
葛尾村エクステンションツアーを行いました
 10/23(土)に葛尾村エクステンションツアーを開催し、10名の学生、社会人、教員に参加いただきました。 常磐道を経由し、浪江IC下車後は葛尾むらづくり公社松本松男さんに浪江-葛尾間の車窓からのガイドや震災時の葛尾村の様子、農業の復興についてお話しいただきました。浪江町の住民は避難の際、今いる場所から離れればいいということで、浪江町中心から30㎞離れた津島支所に避難をしたが、そこには高い放射能を含んだ雪やみぞれが降り注いでおり、そこで1週間程過ごさせてしまったいうことを当時の町長はとても申し訳なく感じていたというお話が印象的でした。 葛尾村郷土文化保存伝習館、葛尾大尽屋敷跡は昨年もお世話になった上遠野さんにガイドいただきました。 伝習館では、珍しい農機具(くさし)や、2011年の震災から現在までの村の変遷がわかるパネル、三匹獅子舞、村に残る270年前に描かれた涅槃仏図などについてお話しいただきました。 葛尾村大尽屋敷は「葛尾村の大金持ち」という意味で、松本一族が最も栄えた8代目葛尾大尽・松本聡通(さとみち)の後妻イネのために作られた庭園や、蔵までの道を水を張って隠したあかずの池などはかすかに面影を残しており、参加者は当時の松本氏の栄華に思いを馳せました。参加者からは、来歴から後妻の話までユニークな話し方で伺えとても楽しかった等の声があった。 午後は2グループに分かれ、圃場見学と昼食をとりました。 圃場で現在育てているえごまを試食、カラシナ、ミニカリフラワーを見学した後、唐箕でえごまの選別作業体験を行い、種と殻を分別した。植物工場ではハウスの設備の違いやマンゴー・トマトの栽培管理について説明を受けました。 昼食時には凍み餅(じゅうねん味、きな粉味)、けんちん汁、フキの甘辛煮の提供がありました。 かつらお胡蝶蘭合同会社の杉下さんからはこの施設や栽培技術、人材育成などについて説明があった後、杉下さんがこの仕事に携わるようになった経緯や葛尾村で熱帯植物を栽培するメリット・デメリットなどについて質疑応答がありました。 ㈱牛屋では、経営者である吉田さん、獣医師である奥様の美紀さん、長男の隼さんの出迎えを受けました。国産羊肉の流通量や牛の肥育鵬について説明を受けた後、その後、翌々日に出荷予定の羊の毛刈りをするということで体験をさせてもらい、4人が毛刈りを体験しました。 ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。
10/23(土)に葛尾村エクステンションツアーを開催し、10名の学生、社会人、教員に参加いただきました。 常磐道を経由し、浪江IC下車後は葛尾むらづくり公社松本松男さんに浪江-葛尾間の車窓からのガイドや震災時の葛尾村の様子、農業の復興についてお話しいただきました。浪江町の住民は避難の際、今いる場所から離れればいいということで、浪江町中心から30㎞離れた津島支所に避難をしたが、そこには高い放射能を含んだ雪やみぞれが降り注いでおり、そこで1週間程過ごさせてしまったいうことを当時の町長はとても申し訳なく感じていたというお話が印象的でした。 葛尾村郷土文化保存伝習館、葛尾大尽屋敷跡は昨年もお世話になった上遠野さんにガイドいただきました。 伝習館では、珍しい農機具(くさし)や、2011年の震災から現在までの村の変遷がわかるパネル、三匹獅子舞、村に残る270年前に描かれた涅槃仏図などについてお話しいただきました。 葛尾村大尽屋敷は「葛尾村の大金持ち」という意味で、松本一族が最も栄えた8代目葛尾大尽・松本聡通(さとみち)の後妻イネのために作られた庭園や、蔵までの道を水を張って隠したあかずの池などはかすかに面影を残しており、参加者は当時の松本氏の栄華に思いを馳せました。参加者からは、来歴から後妻の話までユニークな話し方で伺えとても楽しかった等の声があった。 午後は2グループに分かれ、圃場見学と昼食をとりました。 圃場で現在育てているえごまを試食、カラシナ、ミニカリフラワーを見学した後、唐箕でえごまの選別作業体験を行い、種と殻を分別した。植物工場ではハウスの設備の違いやマンゴー・トマトの栽培管理について説明を受けました。 昼食時には凍み餅(じゅうねん味、きな粉味)、けんちん汁、フキの甘辛煮の提供がありました。 かつらお胡蝶蘭合同会社の杉下さんからはこの施設や栽培技術、人材育成などについて説明があった後、杉下さんがこの仕事に携わるようになった経緯や葛尾村で熱帯植物を栽培するメリット・デメリットなどについて質疑応答がありました。 ㈱牛屋では、経営者である吉田さん、獣医師である奥様の美紀さん、長男の隼さんの出迎えを受けました。国産羊肉の流通量や牛の肥育鵬について説明を受けた後、その後、翌々日に出荷予定の羊の毛刈りをするということで体験をさせてもらい、4人が毛刈りを体験しました。 ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。
浜通りエクステンションツアーを行いました
 延期していた浜通りエクステンションツアーを10/10(日)に行い、12名が参加しました。 これまでは葛尾村を中心に訪問ツアーを行っていましたが、今年度採択された令和3年度「大学等の「復興知」を活用した人材育成基盤構築事業」の一環として、南相馬市・浪江町にも活動範囲を広げていきます。 特に南相馬市については今回は初めての訪問となりました。
延期していた浜通りエクステンションツアーを10/10(日)に行い、12名が参加しました。 これまでは葛尾村を中心に訪問ツアーを行っていましたが、今年度採択された令和3年度「大学等の「復興知」を活用した人材育成基盤構築事業」の一環として、南相馬市・浪江町にも活動範囲を広げていきます。 特に南相馬市については今回は初めての訪問となりました。
浜地域農業再生研究センターの常盤所長からは、ヘアリーベッチをはじめとする緑肥の効果や様々な防護柵における対応獣種とコスト対策などの実証研究事例の紹介、震災前後の農作物の作付面積の比較紹介等のお話をいただきました。学生からの、「なぜトルコキキョウを選んで栽培したのか?」という質問に、他地域での催場実績があるためデータがあったことと、ハウス栽培のため小規模でも始められること、玄人向けの品目のため技術を身につければ小規模でも収益をあげられるためと回答されました。 小高工房の廣畑さんからは、震災当日のご自身とお子さんの様子、避難指示を受けそれから解除された小高区について、3人で15本の苗から始めた唐辛子プロジェクトについて等お話しいただきました。廣畑さんは、「震災とは何か」考えたときに「明日の予定がなくなること」だと感じたそう。
午後は唐辛子の収穫体験をさせていただきました。「緑の部分がなく、胎座がしぼんだ真っ赤なもの」を収穫するよう説明いただき、参加者同士、これはまだ先が緑だ。(列になって端から収穫していたのに)ここ見落としてた!と話しながら収穫を楽しんでいました。これは型コロナウイルスで参加者同士のコミュニケーションをなかなか取れない中で貴重な時間でした。 浪江まちづくり公社の菅野さんには昨年同様請戸地区のガイドをお願いしました。請戸漁港は初めての見学となりました。請戸の漁師は腕が良く、震災前は刺網漁法で生きたまま魚を取り、活魚として東京の市場に卸していたといいます。昨年4月から水産業の共同利用施設・市場が再開し、水揚げが再開したため町内にも新鮮な魚が出回るようになったそうです。 浪江町の津波被災地の方の一番の願いは早くお墓を作ってほしいということでした。そこで町の震災後第一号の公共事業として行われたのが大平山霊園の整備でした。お盆とお彼岸には復興支援の方々で霊園にテントを張り、再開の場としました。 ご協力いただいたみなさま、誠にありがとうございました。
10/23(土)葛尾村エクステンションツアー開催。参加者募集
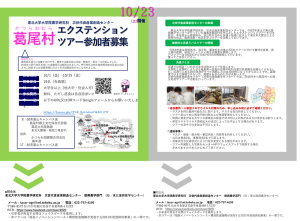 この度、当センターでは採択された令和3年度「大学等の「復興知」を活用した人材育成基盤構築事業」の一環として活動を行うこととなり、その参加者を募集いたします。
この度、当センターでは採択された令和3年度「大学等の「復興知」を活用した人材育成基盤構築事業」の一環として活動を行うこととなり、その参加者を募集いたします。
日時:令和3年10月23日(土)
行程:午前7:50までに農学研究科 青葉山キャンパス集合(厳守)→葛尾村郷土文化保存伝習館→葛尾大尽屋敷跡→昼食→東北大学圃場・植物工場→かつらお胡蝶蘭合同会社→自株牛屋→17:40青葉山キャンパス着
定員:先着20名(座席の間隔をあけてバスに乗車するため)
対象:学生・院生・留学生・教職員
※留学生の方へ:ツアーは全て日本語で行います。
詳細:
・ツアーは無料です。 ・昼食は各自で持参してください。
・参加者には、終日マスクの着用をお願いします。
・バス乗車前に検温し、発熱が確認された場合には参加をお断りする場合があります。
・ツアー途中からの参加、合流等は一切できません。
・新型コロナウイルスの感染状況、また気象状況等により、ツアーを中止または内容の変更をする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
問合せ先:次世代食産業創造センター事務局
022-757-4195/tascr-agri@ml.tohoku.ac.jp(お申し込みはフォームからお願い致します)
※募集チラシの「参加要件」「連絡事項」をご確認の上、以下URLのGoogleフォームよりお申し込みください。 たくさんのご応募をお待ちしております。
農学研究科 次世代食産業創造センター
10/10(日)延期していた浜通りエクステンションツアーを開催
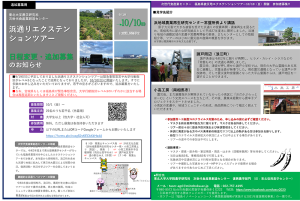 先日9/19(日)ツアーについて延期のご報告をしておりましたが、再開のめどが立ちました。 10/10(日)に開催いたします。つきましては若干名の追加募集を行いますので、ツアー参加をご希望の方は以下URLまたはチラシのQRコードのグーグルフォームからお申し込み下さい。
先日9/19(日)ツアーについて延期のご報告をしておりましたが、再開のめどが立ちました。 10/10(日)に開催いたします。つきましては若干名の追加募集を行いますので、ツアー参加をご希望の方は以下URLまたはチラシのQRコードのグーグルフォームからお申し込み下さい。
日時:令和3年9月19日(日)
行程:午前8:20までに農学研究科 青葉山キャンパス集合(厳守)→福島県浪江町着、「浜地域農業再生研究センター」職員様より講話→浪江町請戸地区見学→道の駅なみえ休憩・見学→南相馬市「小高工房」および畑の見学と講話→18:00青葉山キャンパス着
定員:先着22名(座席の間隔をあけてバスに乗車するため)
対象:学生・院生・留学生・教職員 ※留学生の方へ:ツアーは全て日本語で行います。
詳細:
・ツアーは無料です。
・昼食は各自で持参してください。
・参加者には、終日マスクの着用をお願いします。
・バス乗車前に検温し、発熱が確認された場合には参加をお断りする場合があります。
・ツアー途中からの参加、合流等は一切できません。
・新型コロナウイルスの感染状況、また気象状況等により、ツアーを中止または内容の変更をする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
問合せ先:次世代食産業創造センター事務局
022-757-4195/tascr-agri@ml.tohoku.ac.jp(お申し込みはフォームからお願い致します)
※募集チラシの「参加要件」「連絡事項」をご確認の上、以下URLのGoogleフォームよりお申し込みください。
農学研究科 次世代食産業創造センター なお、参加者多数の場合は先着順とさせていただきます。
マンゴー提供についてメディアに取り上げられました。
「給食でマンゴー味わう 福島県葛尾村の小中学生 東北大大学院が試験栽培」(福島民報)
「特産品目指す葛尾産マンゴーが学校給食に 葛尾村」(NHK)
「葛尾マンゴーの甘さにびっくり 小中学校の給食で提供」(福島民友新聞)
葛尾小中学校の給食にマンゴーを提供しました

9/19(日)浜通りエクステンションツアー(9月)延期のお知らせ
農学研究科 次世代食産業創造センターでは、「復興農学」をはじめとする講義科目の開講や、福島県内の被災地への見学ツアー等、被災地における農業の復興を先導する人材の育成を行っております。そうした取り組みの一環として、連携を結んでいる福島県南相馬市・浪江町において、エクステンションツアーを開催することとなり、そのご案内をさせていただいておりました。しかし、9/12(日)まで宮城県では緊急事態宣言が発令されており、それ以降もまん延防止等重点措置期間となる予定です。それに伴い学内の新型コロナウイルスに対する行動指針もレベル3にあがっています。そのため、今回のツアーは延期する決定をいたしました。次回の開催時期は未定となっておりますが、決定次第ご連絡させていただきます。開催時期、また実施の際も予防を徹底して行ったうえでの開催といたしますので、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
問合せ先:次世代食産業創造センター事務局
022-757-4195/tascr-agri@ml.tohoku.ac.jp
農学研究科 次世代食産業創造センター
センター長 阿部 敬悦
復興農学部門長 小倉 振一郎
9/19(日)浜通りエクステンションツアー開催。参加者募集
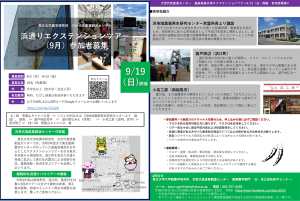 この度、当センターでは採択された令和3年度「大学等の「復興知」を活用した人材育成基盤構築事業」の一環として活動を行うこととなり、その参加者を募集いたします。
この度、当センターでは採択された令和3年度「大学等の「復興知」を活用した人材育成基盤構築事業」の一環として活動を行うこととなり、その参加者を募集いたします。
日時:令和3年9月19日(日)
行程:午前8:20までに農学研究科 青葉山キャンパス集合(厳守)→福島県浪江町着、「浜地域農業再生研究センター」職員様より講話→浪江町請戸地区見学→道の駅なみえ休憩・見学→南相馬市「小高工房」および畑の見学と講話→18:00青葉山キャンパス着
定員:先着22名(座席の間隔をあけてバスに乗車するため) 対象:学生・院生・留学生・教職員
※留学生の方へ:ツアーは全て日本語で行います。
詳細:
・ツアーは無料です。
・昼食は各自で持参してください。
・参加者には、終日マスクの着用をお願いします。
・バス乗車前に検温し、発熱が確認された場合には参加をお断りする場合があります。
・ツアー途中からの参加、合流等は一切できません。
・新型コロナウイルスの感染状況、また気象状況等により、ツアーを中止または内容の変更をする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
問合せ先:次世代食産業創造センター事務局
022-757-4195/tascr-agri@ml.tohoku.ac.jp(お申し込みはフォームからお願い致します)
※募集チラシの「参加要件」「連絡事項」をご確認の上、以下URLのGoogleフォームよりお申し込みください。
たくさんのご応募をお待ちしております。
農学研究科 次世代食産業創造センター
あぜりあにてトマトの試食配布を行っています

次世代食産業創造センターを設立しました
生物多様性応用化学センターと東北復興農学センターが統合して、令和3年4月に次世代食産業創造センターを設立しました。旧センターの活動を引き継ぐとともに、急速に進む少子高齢化、過疎化に対し、農林水産・食品産業の維持発展と自然共生による生物多様性の維持を両立させ、持続可能で自立した東北地域を構築するための研究・教育を行ってまいります。