生物海洋学分野
生物海洋学
研究室のメンバー
メールアドレスは*を@に変えてください
教授 大越 和加 (おおこし わか) waka.sato-okoshi.d3*tohoku.ac.jp
出身地 宮城県仙台市
趣味
世界中のさまざまな土地に出かけ、そこの空気を吸い、音を聞き、ぶらぶら歩くことが好き。
多様性を五感で感じることができます。
研究テーマ
「環形動物門多毛類の生物学、分子生態学」「種々の攪乱が海洋生物に及ぼす影響」
「極海や深海の生物学」などに取り組んでいる。
プランクトンとベントスを切り離して考えるのではなく、それらを繋いで海洋を理解する。
とくに、環形動物門多毛類に焦点を当て、幼生(プランクトン)と成体(ベントス)の両方を研究している。
海洋生態系において環形動物門多毛類は貝類、甲殻類とともに三大構成生物群といわれ、大きなバイオマスを有し、多様性に富み、あらゆる海洋の環境に適応しています。環形動物門多毛類は生態系において重要な役割を担っているにもかかわらず、人間との関係が他の動物門に比べ見えにくいためにまだよく理解されていません。例えば、人間は環形動物を積極的に食物として利用していませんが、人間以外の動物は環形動物を重要な餌生物としているほか、環形動物は水質の浄化、底質の浄化、生物攪拌、有機物分解、物質循環などの機能において欠かすことのできない大切な生物群です。世界には多くの環形動物研究者がいますが、彼らと協力し合い、海域をつなぎながら楽しく研究を展開しています。一度、環形動物を見に、研究室へ足を運んで下さい。その一歩が、海洋生態系の維持と安定を担う、未知の環形動物の研究の扉を開けることに繋がります。
一言
普遍性と多様性。分断せずに繋ぐこと。根を持つこと、翼を持つこと。
准教授 西谷 豪 (にしたに ごう) ni5@tohoku.ac.jp
出身地 愛知県津島市
趣味 ソフトボール
研究テーマ(詳しくは下記リンクをクリックしてください)
寄生性渦鞭毛藻を利用した赤潮・貝毒発生防除への新たな可能性
宮城県東松島市における微細藻類バイオマス研究
三陸沿岸域に生息する二枚貝幼生の分類と生態調査
宮城県石巻湾における麻痺性貝毒原因生物のモニタリング
アジア圏における赤潮原因プランクトン夜光虫の流動ダイナミクス
一言
プランクトンのなかには有害な種類もいますが、人の役に立つ有用な種類もいます。
有害なプランクトンの現場生態を明らかにして養殖産業への被害を軽減したり、
有用なプランクトンの分布、探索、増殖条件の解明を行なっています。
現在は、有害有毒プランクトンを殺滅する寄生生物の研究について、最も力を入れています。
全国で赤潮や貝毒による被害が多発しています。私たちの研究グループは、
その原因となっている有害有毒プランクトンの天敵(寄生生物)を発見しました。
近い将来、この寄生生物を「微生物農薬」として全国の海域に導入し、
安定した水産業に貢献することを目標にしています。
また、この特殊な寄生生物を研究しているのは、
日本では当研究室のみであり、日々新しい発見が続いています。
その発見を一緒に行える学生さんを募集しています。
中高校生や大学生の研究室見学も歓迎いたしますので、
メールにてお気軽にご連絡ください。
学生
| 学年 | 名前 | 研究対象、フィールド |
|---|---|---|
| D3 | 永井 優貴 | ベントス(多毛類)、蒲生干潟 |
| D3 | Muhammad Izzat Nugraha | プランクトン(夜光虫)、インドネシア |
| M2 | 貴志 龍太郎 | ベントス(多毛類)、蒲生干潟 |
| M1 | 落合 慶亮 | プランクトン(寄生生物) |
| M1 | 川村 迅 | プランクトン(寄生生物) |
| M1 | 堀江 優太 | ベントス(多毛類)、女川湾 |
| M1 | 岡田 優花 | プランクトン(麻痺性貝毒原因生物) |
| B4 | 上野 春馬 | |
| B4 | 坂田 勇介 | |
| B4 | 谷口 真萌 | |
| B4 | 前野 めぐる | |
| B4 | 山尾 汰一 |
2024年10月 青葉山キャンパスにて

2023年10月 青葉山キャンパスにて
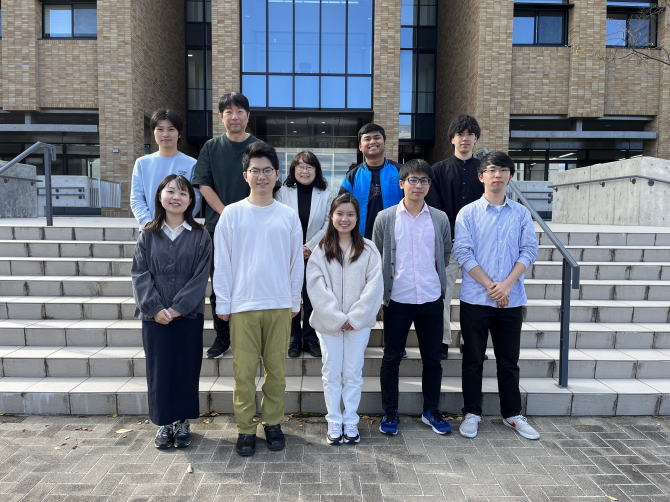
2022年5月 青葉山キャンパスにて
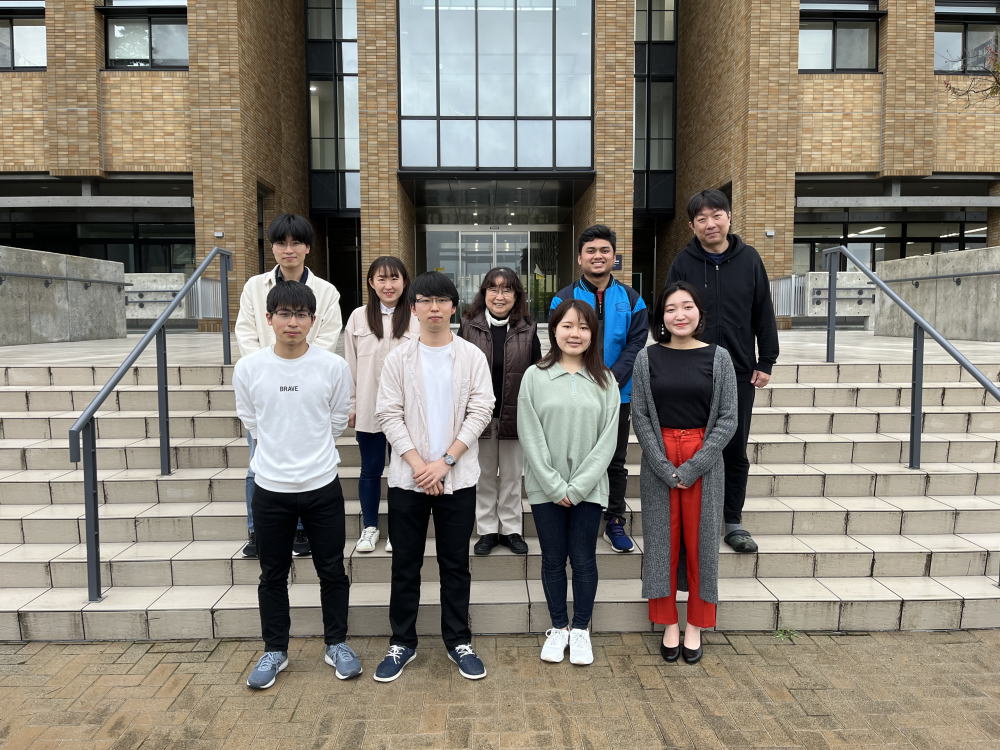
2021年5月 青葉山キャンパスにて(新型コロナウィルスの影響により、教員と学部4年生のみ)
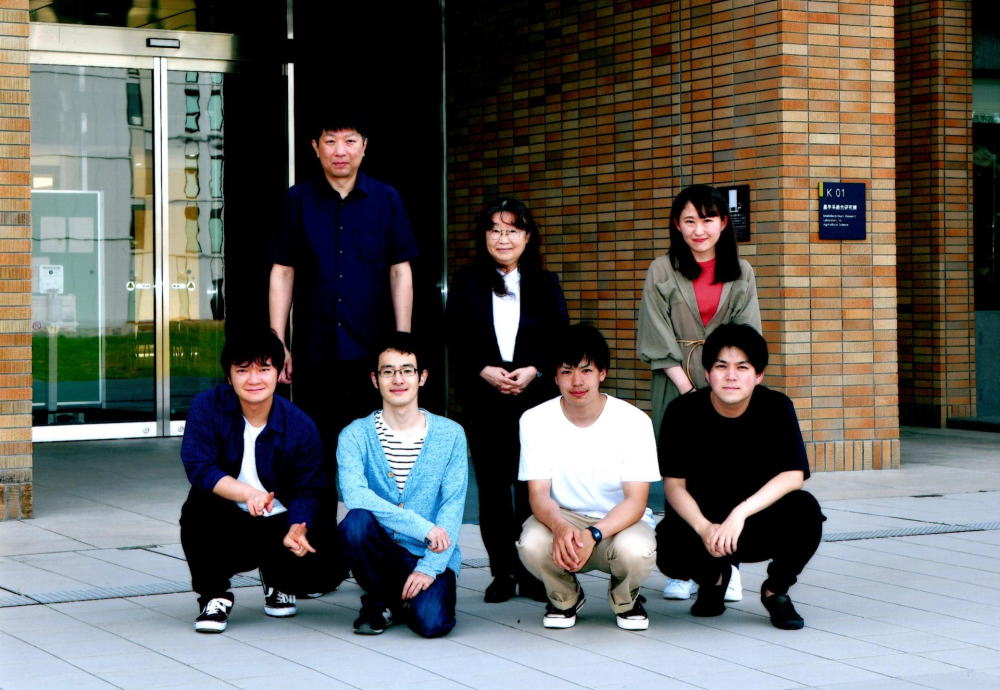
2020年5月 青葉山キャンパスにて(新型コロナウィルスの影響により、教員と学部4年生のみ)
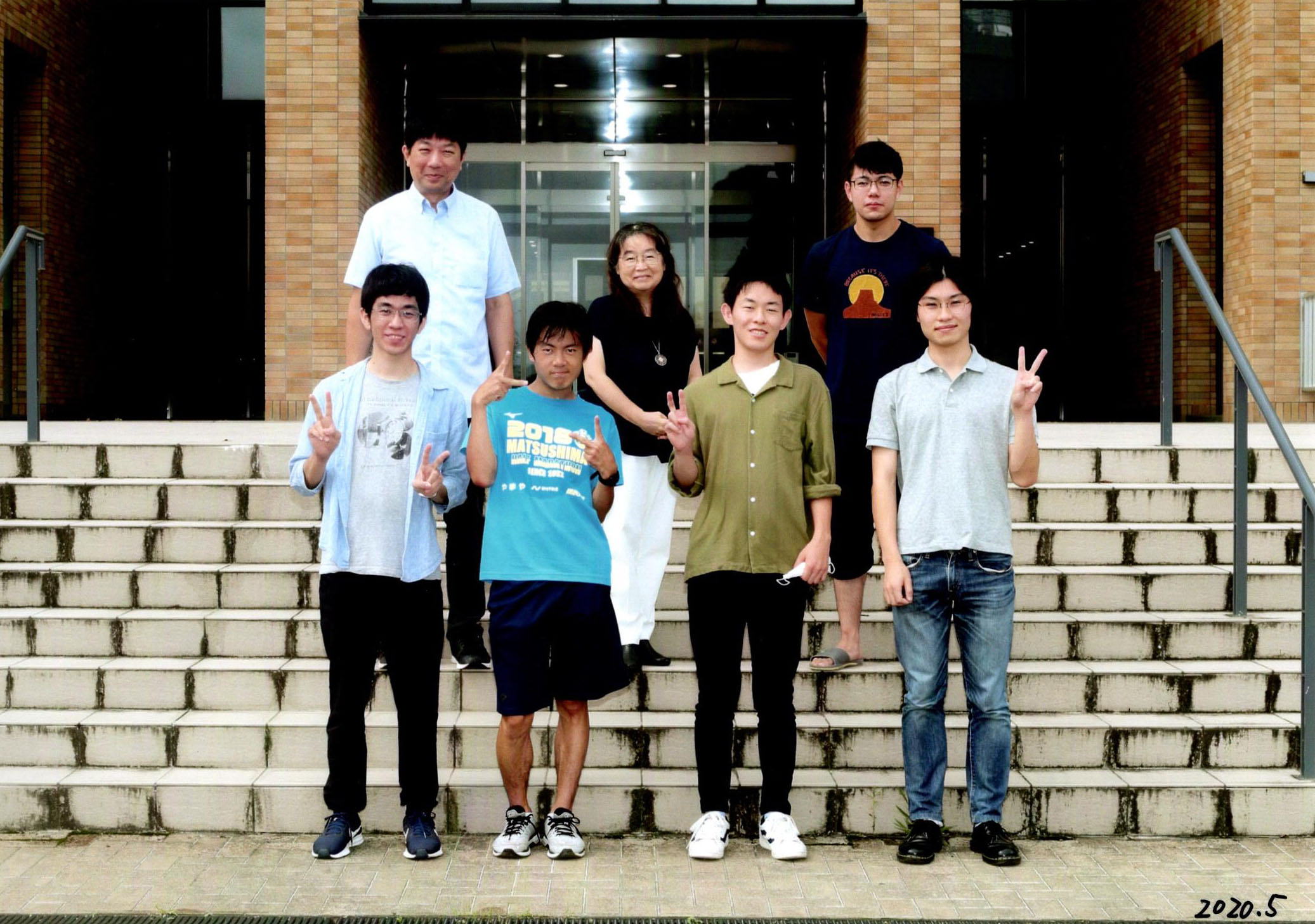
2019年5月 青葉山キャンパスにて
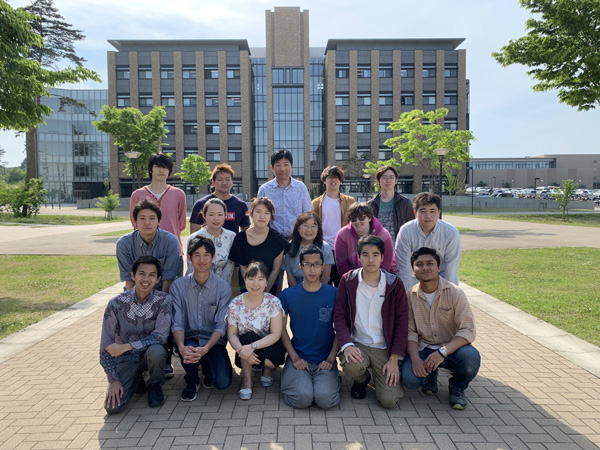
2018年5月 青葉山キャンパスにて

2017年5月 青葉山新キャンパスにて

2016年10月 最後の雨宮キャンパスにて

2015年5月 農学部構内にて

2014年5月 農学部構内にて
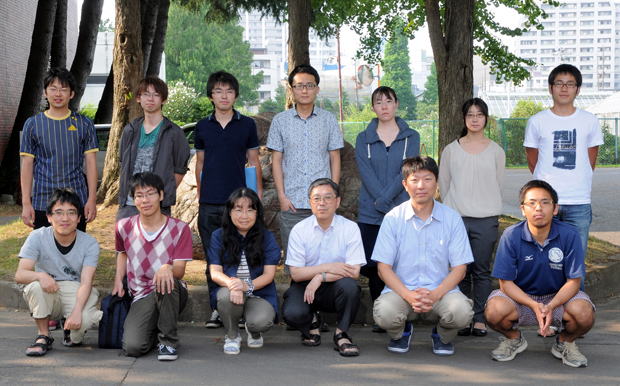
2013年5月 農学部構内にて

2012年5月 農学部構内にて

2011年5月 農学部構内にて
