2014年(平成26年) 授業の様子
2015年3月25日(水):JFSおよびFS認定証授与式(第一期生)
3月25日の東北大学農学部・農学研究科で行われた学位記授与式において、第1期JFS(ジュニアフィールドスペシャリスト)およびFS(フィールドスペシャリスト)の認定証が駒井三千夫農学部・農学研究科長(兼 東北復興農学センター長)より授与されました。 認定者は、以下の方です。
■JFS(ジュニアフィールドスペシャリスト)8名
・金森 眞紀(かなもり まき)さん:農学部
・黒瀬 開(くろせ かい)さん:農学部
・菅波 眞央(すがなみ まお)さん:農学部
・高田 萌(たかだ もえ)さん:農学部
・瀧澤 修平(たきざわ しゅうへい)さん:農学部
・西村 翼(にしむら つばさ)さん:農学部
・石川 未紗(いしかわ みさ)さん:経済学部
・真壁 拓仁(まかべ たくと)さん:農学部
■FS(フィールドスペシャリスト)2名
・渥美 敦順(あつみ のぶよし)さん:農学研究科
・金 ?(きん きん)さん:農学研究科

この度、認定されました皆様におかれましては、誠におめでとうございました。今後のご活躍を、心よりお祈り申し上げます。
2014年9月27日(土):復興農学マイスター・IT農業マイスター(第1期生)の認定式
9月27日(土)、天気に恵まれ、澄みきった青空に秋を感じる中、復興農学マイスター・IT農業マイスター(第1期生)の認定式を行いました。
東北復興農学センターの全10回の講義及び全4日間の実習を受講し、復興農学マイスター(CAR)50名(社会人27名、学生23名)、IT農業マイスター(CAIT)44名(社会人25名、学生19名)が第1期生として認定されました。



復興農学マイスター(CAR)代表挨拶の様子

IT農業マイスター(CAIT)代表挨拶の様子

式典後は、校内で記念撮影を行いました。東北復興農学センターの第1期生となった皆様の、これからのご活躍を期待しております。
【全講義を終えて、マイスター認定者の感想より】
グループ議論を通して、新たな力を得た様に感じております。人と人とのネットワークも多いに私にとっての宝となりました。(社会人) 自分のやりたいことを考える指針となった。(農学部1年)
復興について同世代の人や年上の方と真面目に語り合いができたこと、そして色々な人に会えたことがプラスになりました。 (農学研究科前期1年)
社会人の方々や自分の知らない業界の方々と話すことで価値観の幅が広がった。色々なことに積極的にチャレンジするようになった。 (農学部4年)
話し合いの進め方について考えるきっかけになり、目的をもった会議ができるようになりました。 (農学部4年)
大規模集団化と併行して、中小経営規模に見合った協業化を働きかけながら、とくに若手の生産者の支援を考えていきたい。ITを活用しながら有機農法を普及させたい。(社会人)
講義のみでなく、ディスカッションを取込まれたことにより、講義により集中参加することができました。IT農業マイスターでは、個々人が機器に触れて実習体験して見たかったです。(社会人)
2014年9月7日(日):IT農学実習3日目
8月31日(日)、9月6日(土)、9月7日(日)と3日間に渡ってIT農学実習を行いました。
1日目は、IT農業の基礎知識について、2日目は、環境センサーや遠隔監視、ネットワークカメラの設置についての講義でした。
3日目は、片平キャンパスのさくらホールにて、IT農業の未来についての講義を受けた後、グループディスカッションを行い、各自発表しました。




【参加者の感想より】
受講前はAIと聞くと植物工場のような大きくてカッチリとした施設を思い浮かべていました。しかし受講後にはAIという言葉から人の顔が想像されるようになりました。講義でネットワークカメラやSNSの利用について説明を受けたことで、思っていたよりも規模が小さいというか、身近というか、今ある農業の形でも割と取り入れやすいように開発されているものも多いのだとわかりました。先生の話にもありましたが、科学を生かすためのAI、農業ではなく、助けを必要としている特定の農業従事者のために、そのプロセスとして科学を用いる、というイメージにつながったと思います。(農学部3年)
受講前は、AIというと専門的で難しく、操作ができる人がかなり限られているのではないかと思いましたが、年代問わず様々な方が使うことが出来て生活に密着したものであることを教えていただきました。価格も安価であることから、仕事である地域づくり、まちづくりの分野において、今回学んだことを生かして地域の皆さんとディスカッションしていきたいと思います。(社会人)
2014年8月30日(土):被災地エクステンション
こちらは、「復興農学フィールド実習」と「IT農学実習」の共通実習として、希望により〔仙台東部コース〕と〔東松島コース〕に分かれて行いました。

〔仙台東部コース〕の様子

荒浜生産組合や植物工場の見学を行いました。

午後は、3つのテーマに分かれて議論し、それぞれプレゼンテーションを行いました。
【参加者の感想より】
講義で学んでいた水耕栽培について、実際の栽培システム、経営状況、将来の農業における水耕栽培(株式会社みちさき)の立場や役割を聞けたのでとても興味を持った。研究テーマであるメタン発酵がみちさきとコラボできると思うので、水耕栽培についてさらに調べていきたい。(農学部4年)
何をするにも、ニーズの調査が大事ということが分かった。また、地域の農地貸し借り問題について、知らなかった知識を得ることができた。新しく農業をする人と、長く農地をもって農作業をしている人との差みたいなものは日ごろ感じていて、もっと今後も色々な意見を感じたいと思いました。(社会人、行政)
これまでの講義、先日の川渡実習、今日のエクステンションと、研究と現場の両面を見ることができました。夢のある研究と、お金や生活費のかかる現実のギャップがよく見えたと思います。復興を考える上で、どうやってお金を儲けるかは大事な事で、将来を見ながら、生活と改革を両立することの難しさがあることが見え、行政と現場、学問の各分野の力をどのタイミングで集約するかが、今後の農業の中で大事という事だと思います。(社会人、教育関連)

〔東松島コース〕の様子

野蒜(のびる)地区や、ディスカバリーセンター等を見学しました。

被災地の現状についてレクチャーを受けた後、グループディスカッションをし、各自発表しました。
【参加者の感想より】
一年生のときに女川に行って以来二度目の被災地訪問でした。土地は違っていますがやはり震災被害の大きさを感じられて胸が痛みました。今回は、みらい都市に選ばれているだけあったのでベルトコンベアなど、すごい復興技術を見られて感動しました。ディスカッションや講話で様々な話が聞けたのはもちろん、実際に訪問したことで、ぼんやりとしていたイメージが見えたのでとてもいい経験になりました。(農学部3年)
東松島市の視察を通して、被災地の現状や復興について肌で感じることができた。今まで復興農学の講義を受けてきたが、以前と比べて東北地方についてよく知ることができたと思う。話し合いや意見の共有が必要であるという声が多く見受けられた。しかし、それを受け止める機関等の存在も大切だと感じた。今回のようなツアーも面白かったが、また個人的にも訪れてみたい。(農学部3年)
野蒜はボランティア等で何度も訪れたりと身近な地域でしたが、この様な機会で改めて見学すると新たな発見等がありました。ディスカッションでは若い人達と意見を交す事が出来て有意義でした。年代が変ると視点も全く違い新鮮です。これからも機会があれば様々な人達と意見を交わしたいと思います。(社会人、IT企業)
2014年7月25日(金):復興農学フィールド実習
7月25日より2泊3日の復興農学フィールド実習を行いました。岩沼、塩釜、田尻、川渡と、様々な実習地で活動しました。



30度を超える猛暑の中、水田調査の様子。

最終日は、班ごとに議論を重ね、素晴らしいプロジェクト発表でした。

最終日は、班ごとに議論を重ね、素晴らしいプロジェクト発表でした。
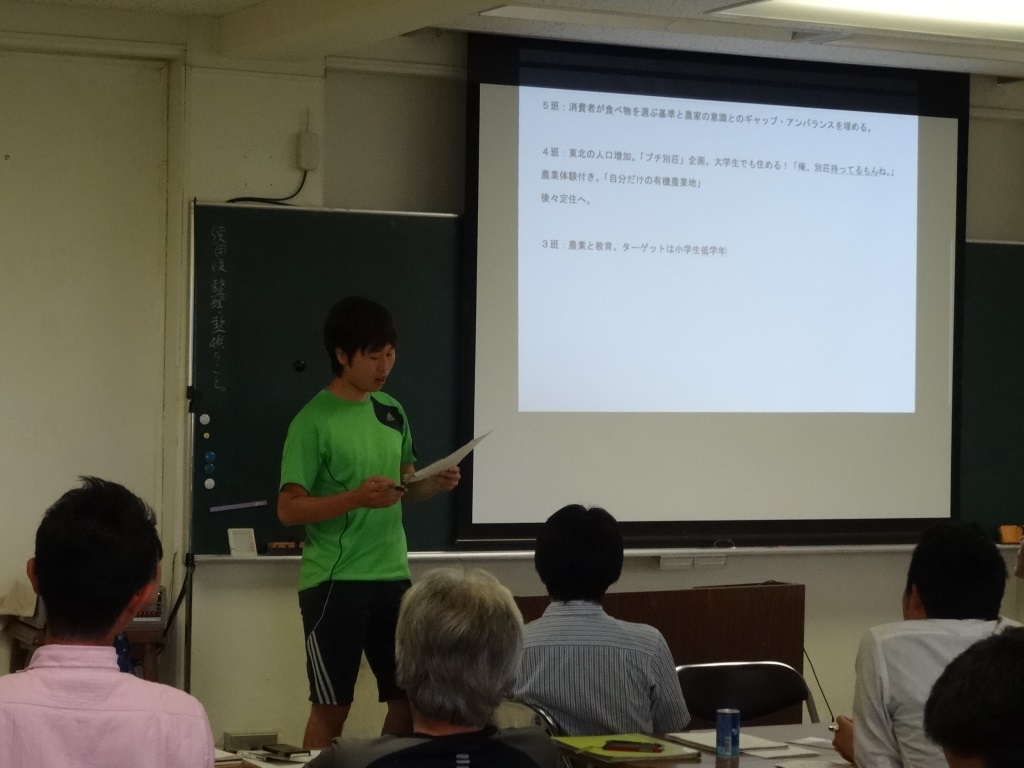
【参加者の感想より】
3日間の実習と最後の報告会を聞いて学生さんの若いアイディアと素晴らしい講師陣でとてもいい体験であった。益々、農業への関心を深める事ができ、様々な問題提起を持ちながら実務にも発展できるよう努力していきたい。ここで出会った人脈を大切に、楽しい農業をしていきたいと思う(社会人、農業)
座学で知識を得るだけでなく、直接五感を使って実感できたのがかなり印象に残った。年齢、世代を超えて意見を出し合うという普段の学生生活ではできない経験ができてうれしかった。(農学部2年生)
技術的スキルが要求される理系学問において、技術と人がこれだけ結びつけられるのは本当に珍しいと思います。今後の生き方に、得たものを必ず活かして何かを生み出していきます。(農学部4年生)

写真:田尻の蕪栗沼(降車したバスはずっと向こうです。)
2014年6月27日(金):第7回目 復興農学講義
6月27日、10番講義室にて学生班は南條先生、2番講義室にて社会人班は多田先生の講義を行いました。

学生班:講義中の様子

社会人班:ディスカッションの様子
2014年5月16日(金):復興農学講義の開講式および第1回目講義
5月16日、東北大学大学院農学研究科(雨宮キャンパス)の第1講義室にて18:00~開講式、18:30~復興農学講義第1回目の講義を行いました。
初日であるこの日は社会人45名、学生43名が出席しました。
開講式では、中井副センター長より東北復興農学センターの概要や講義スケジュール、授業テーマについてご紹介しました。

学生班:講義中の様子

